
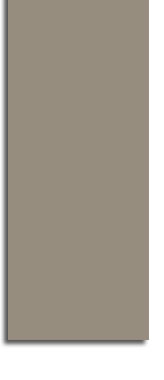


|
風のかたち
|
||
|
|
||
| 五月、収穫を待つ玉ねぎは丸々とした姿を地上に並べ、隣同士がくっつき合い、「もうこれ以上収穫が遅れると地下に向かって伸びるしかない」と、言わんばかりの光景が広がっている。
海をわたる潮の香りが畑をわたる草と土の香りに変わり、やっとこの島に着いたことを実感する。 その香りには、体中の細胞の隅々にまで染み込んでいくような懐かしさがある。 そして都会から離れられた安堵した気持ちと、これから一年におよぶこの島での暮らしへの、不安な気持ちとが静かにこみ上げてくる。 玉ねぎ畑に囲まれた住まいの三方は山が迫り、東が海に向かって開けている。背後の山は深く、五月雨に神秘的に煙っている。 人びとは平地に暮らし、深い山々は昔のままの姿を今にとどめている。 収穫の始まった玉ねぎ畑では、農夫が一日中腰を丸めて働いている。 引き抜かれた玉ねぎは見る見る土の上にきれいに並べられ、選別され、荷車に載せられる。 これらは直ぐに出荷されるのではなく、玉ねぎ小屋と呼ばれる柱と屋根だけの小屋の中に何段にも吊るされて出荷の時を待つことになる。 風が吹くと、吊るされた玉ねぎの匂いが風に乗ってやってくる。 山に降った雨を集めて、天川(あまがわ)が流れている。 鬱蒼と茂った木々の中にあって、そこから聞こえてくる水音だけが、そこに川のあることを知らせようとしているかのようだ。 月が替われば、この川の水は次の出番を待つ畑にと注がれる。 その日まで農夫はせっせと苗代を作り育て守り続ける。 窓の向こうに見える海は、春の光を反射して、さざ波の形がここからでもわかる。 春の日差しも、これからだんだんと夏のものに変わっていこうとしている。 六月、畑に水が注がれ、土が掻き回され、畦がつくられる。 それにしても農夫はよく働く。 畦は休みなしに、一気に作る。辛い仕事は辛抱強く、坦々とこなすのが昔からの農民の知恵。 畦を見ながら子供の頃の話を思い出す。 母が一生懸命畦づくりをし、やれやれと後ろを振り向いたら、幼い私が畦の上に立っていた。 畦の上には小さな足跡が続き、叱ることもできず、父と顔を見合わせて笑ったという話。 窓からの光景に、そんな昔の話を思い出す。 玉ねぎ畑も田んぼに変わり、梅雨の雨を待つ。 雨を待って、田植えが始まる。 苗代で大事に育てられた苗が規則的に整然と植えつけられていく。 田んぼというのは水さえ張っていればよいというものではないらしい。 水に浸かる苗の長さは水を流し出す堰の高さで決まる。 窓の外の光景は、農業とはなんと科学的なものだということを教えてくれる。 それにしても不思議なのは田んぼに水が入ると、蛙が湧いてくることだ。 夜ともなると、彼らの合唱が、張った水に反響して眠ることもおぼつかない。 五月にはまだあまり上手く鳴けなかった鶯も、「ホー、ホケキョ」と、天性のごとく自慢気に鳴いている。畑だった時は、山鳩のつがいが、「クッククー、クックルクー」と、鳴きながら、仲良く餌を啄ばんでいたが、今は燕が舞っている。 燕を見ていると数年前の東京での出来事を思い出す。 壊されて落ちていた巣の傍で、「ピーピー、ピーピー」と、騒がしく鳴いていた二羽の雛。 見捨てることもできず、この二羽の子育てが始まった。 私は餌の調達係になり和牛、黒豚、地鶏のササミと、次々と楊枝の先に付けて口元に運ぶが、どれも食べようとしない。「やはり生き餌かあ!」と、蟻、蝶、バッタと昆虫採集が始まった。やっと蝶を少し食べてくれたが、都会での餌探しは大変な難事。 幸いサザエを食べてくれ、なんとか食料確保の目途がつきほっとした。 一方、妻は燕の巣に似せて、紙で巣を作り、色鉛筆で着色。 そして、その中に壊れた巣から掻き集めた羽毛などをそっと入れた。 やっと飛べるようになった雛を、親鳥のもとに帰す時に、きっと来年は我が家のベランダ裏に巣を掛けに戻って来ると淡い期待を抱いたが、あの時やっと飛べて、電線につかまってこっちを振り向いた姿が最後になった。 そして今、目の前の田んぼを地面すれすれに燕たちは飛んでいる。 ここでの生活はシンプルそのもの。 テレビもエアコンも拒絶した、質素な暮らし。 眠くなれば眠り、日の出と共に目覚める。朝、新聞の配達が待ち遠しいこともしばしばある。 コンビニも自動販売機もない。「ほたる」という名のお好み焼き屋が一軒あるだけ。 天川のそばにある蛍という名が気に入っている。 ただ一本の電話が外の世界とつながっている。 電話がつくまでは、歩いて公衆電話まで行った。 海に面して立っているこの電話からかけると、船の音、波の音、風の音が聞こえて来るようだと、東京にいる妻が言う。 きっと妻も脳裏に焼き付いたこの風景を受話器の向こうで重ね合わせているのだろう。 妻は時間をつくってはこの島にやって来る。 時間が経つにつれ、私の帰京は少なくなり、妻の来島ガ多くなった。 きっと二人とも、この島が気に入っているのだろう。 島がというより、島での生活が気に入っているのだろう。 この島の自然も人情もみんな気に入っているのだろう。 一人の時は自分で料理をつくる。 最初の頃は食べたものを官製葉書に書いて、絵を添えて妻に出した。 そのうち四国の阿波和紙と出会い、和紙の葉書に絵を書いて、短文を添えたものへと変わった。 その変化の中に、都会生活の中でなおざりにしてきた、内的なものを充実する機会をこの島で得て、その一つを素材というものを通して表現しようとしている自分を感じる。 二人で始めた一人暮らしの中で二人とも、自分を素直に表現するということ、そして自分の人生を大切に生きるということを見つめ直してみようと考えるようになって来ている。 妻は東京での仕事を調整してこの島にやって来ると、散歩に出て、猫や犬や牛と挨拶を交わし、料理をしたり、本を読んだり、昼寝をしたりと自分の時間を楽しんでいる。 田舎というのは誰かが、何処からか見ているらしい。 妻が来ると、どうも回りの人たちとの接触の機会が増えるようだ。 妻は皆から声をかけられる。私は妻が見知らぬ誰にでも、通りすがりに頭を下げて挨拶をするのがとても好きだ。 一緒の時も頭を下げながら歩いている。 二人で小さな島に渡って、貝を採ったりワインを飲んだり、乳搾りに挑戦したり、山を探検したりという時を過ごすのも楽しい。 しかし、二人で過ごす数日間はあっという間に過ぎ、また二人の一人暮らしが始まる。 七月、梅雨が明けると夏の空がやってくる。 今まで煙っていた海の向こうの島影もくっきり見える。 東に向いた窓から見える海は、朝日を浴びてそこの鏡でもあるかのように、金色に輝く。 変わらない風景の背後にある海だけがいろんな色に変化する。 窓から見える海の中でも、屋根と屋根で切り取られた海が好きだ。 そこは無限の奥行きを持つ舞台のように、水平線の向こうから大きな船が現れたり、消えて行ったり、手前を小さな漁船が行き交ったりと、飽きることがない。 そして時々、「ボー、ボー」と、汽笛の音が趣を添える。 漁船の音は、「ポンポンポンポンポン」と騒がしいが、その音の中に漁師のなりわいが見えてくる。 漁師の夫婦は仲が良い。小さな船を二人で操るため、二人の呼吸が大切なのだ。 海からの収穫を共有している満足感が、二人の日焼けした笑顔にうかがえる。 農夫の夫婦が淡々と自分の仕事をこなしているのと対照的に、そこは狭い船の上、やはり、少し夫婦の形も違ってくるのだろう。 ここに住むことにしたのは、漁師町が近いということもあった。 重なるように建つ家々、狭い路地が迷路のように続き、その先に海がキラキラと光る。 心地よく漁船の音が響き、人々の生活の音が聞こえてくる。 この閉鎖的な共同社会、しかし温かい心を持つ人々の住む町。 猫も犬も人も、皆一緒に暮らしている。 家々の軒裏には燕が今年も巣を掛け、それが当たり前のことのように季節が繰り返す。 その巣を傷つけるなど、考えもしない人びとが暮らす世界がここにはある。 家に庭などない。 それ程高密度に集合した家々から、ピアノの音が聞こえたり、御輿小屋の中から夏祭りの練習の笛や太鼓の音がする。 都会では騒音でも、ここでは心地良い音色として響いてくる。 それはきっと心のスタンスの問題なのだろう。 この町にも夏を向かえ、島外からの観光客が増える。 よそ者が多くなったなあと、東京から来ているよそ者が思う。 しかしそう思うのも、すでにこの島の人になっている証かもしれない。 暑い夏もあっという間に過ぎてゆく。 もう少しゆっくり時が流れて欲しいと願う。 ここでの暮らしも、もう四分の一が過ぎようとしている。 窓の外には玉ねぎが吊るしてある。 風に揺れるその姿を見ていると、五月の収穫の頃を思い出す。 額に汗して収穫に勤しむ老夫婦に、大変ですねと声をかけたら、袋いっぱいに詰めてくれた八十八個の玉ねぎのこと。 東京の友達に絵手紙を添えて送ったこと。いろんな料理を試みたこと。 この玉ねぎの味が私をこの島の人にしたのかも知れない。 この島で自分の生き方を見つめ直す機会を得て、都会での暮らしが人間として、正しい選択なのかという迷いが生じている。 都会での暮らしを選択した代償として、生まれた時に平等に授かった尊い感性を、一つまた一つと無くしていくような、そんな気がしてならない。 八月、水平線の上に入道雲がいくつも見える。 田んぼの苗も稲と呼べる長さになってきた。 細かった葉もたくましくなってきた。 トンボが飛び交い、天川の茂みの中では蝉がせわしく鳴いている。 都会では忘れがちな季節が、ここには確実に存在する。 心地良い風が稲の絨毯の上を吹き過ぎる。 葉先は一緒になびいたり、列ごとにお辞儀を繰り返したり、波のようにうねったり、フラダンスのようにくねったり、つむじのように渦を巻いたり、百面相のように変化する。 それらを眺めながら、「これが風のかたち」と、ふと思う。 夏も終わり、季節も変わっていく。 稲穂が黄色く実り、重く頭を垂れて刈り入れをむかえる時がやがて来る。 空が赤とんぼの色に染まり、刈り取られた後の切り株が、整然と植えられた苗がぎこちなく風に揺れていた、あの初夏の日のことを思い起こさせる時がきっと来るだろう。 そしてまた、玉ねぎを収穫する季節が巡ってくる。 |
||
 |
||
|
|
|
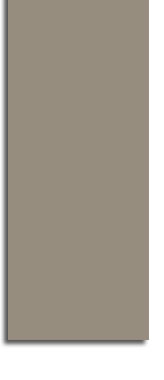 |
 |
||
 |
||
|
|
||